To view this content, you need to sign in.
You should only be asked to sign in once. Not the case? Click here
Register now to access this content and more for free.
日系企業が見る国際アライアンス加盟の意義とその背景②
You should only be asked to sign in once. Not the case? Click here
Register now to access this content and more for free.
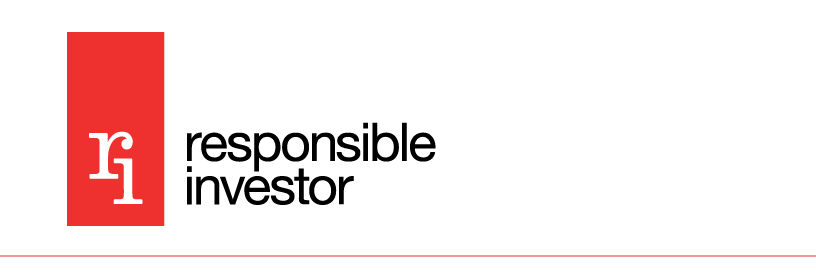
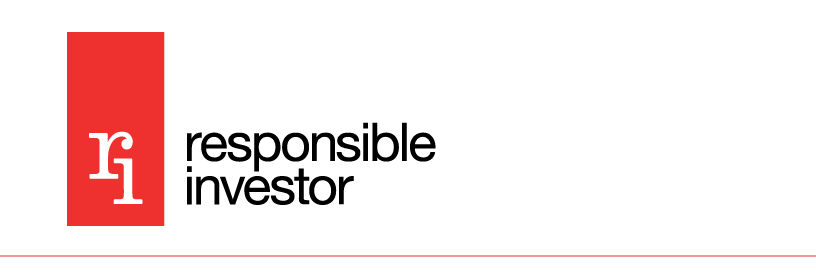
Copyright PEI Media
Not for publication, email or dissemination